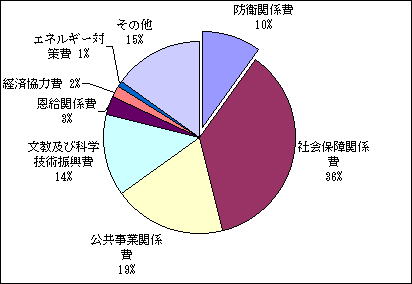 (資料1,2ともに、防衛庁ウェブサイトより引用[1])
(資料1,2ともに、防衛庁ウェブサイトより引用[1])防衛費1%枠問題
1.はじめに
AHPを用いて、対GNP比約1%の防衛費の規模が適正かどうかを決定する。防衛費1%枠やそれをめぐる社会情勢に関しては、参考資料を参照する。
2.問題の階層構造化(分析1)
(ア)意思決定問題:どの程度の防衛費が望ましいか。
(イ)評価基準:多極化時代に即応した日本の外交関係樹立に与える影響(国際関係)
防衛費総額が国内経済に与える悪影響の少なさ(経済)
国内政治に与える悪影響(野党の反発)の少なさ(国内政治)
国民の不満や不安の少なさ(社会問題)
(ウ)代替案:現行1%枠の維持(現行維持)
枠の引き上げ(引き上げ)
枠の撤廃(撤廃)
(エ)問題の階層化(テキストp90、図6.1参照)
(オ)第2層(レベル2)の一対比較とウェイトの計算(テキスト参照)
(カ)第3層(レベル3)の一対評価とウェイトの計算(テキスト参照)
(キ)ウェイトの総合化
表1)各評価基準と代替案のウェイトの総合化
|
評価基準 |
国際 |
経済 |
政治 |
社会 |
総合ウェイト |
|
|
ウェイト |
0.63
|
0.20 |
0.08 |
0.09 |
|
|
|
現行 |
0.64
|
0.73 |
0.65 |
0.69 |
0.661
|
|
|
引き上げ |
0.26
|
0.19 |
0.28 |
0.22 |
0.243 |
|
|
撤廃 |
0.10
|
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.096 |
|
「現行」の総合ウェイト=0.63*0.64+0.20*0.73+0.08*0.65+0.09*0.69=0.661
3.感応度分析(分析2)
評価基準のうち、国際関係の定義を変えてウェイトを出してみる。はじめの分析においては、「多極化時代に即応した日本の外交関係樹立に与える(プラスの)影響」ということで、ソ連(ロシア)やアジア、中東との国際関係を重視し、防衛費の増額はそのマイナス要因であるとして評価した。この定義を「日米関係に重点をおいた日本の外交関係樹立に与える(プラスの)影響」に変え、防衛費の増額そのプラス要因であると評価して分析を行うと、次のような結果になる。
表2)対米関係を重視した総合ウェイト
|
評価基準 |
国際 |
経済 |
政治 |
社会 |
総合ウェイト |
|
|
ウェイト |
0.63
|
0.20 |
0.08 |
0.09 |
|
|
|
現行 |
0.11
|
0.73 |
0.65 |
0.69 |
0.331
|
|
|
引き上げ |
0.54
|
0.19 |
0.28 |
0.22 |
0.420
|
|
|
撤廃 |
0.35
|
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.249
|
|
4.テキスト以外の分析
(ア)階層の追加(分析3):
対米関係を重視するか対米関係以外を重視するか、どちらか一方だけを評価基準にするのではなく、国際関係の下にもう一層評価 基準を置き、それぞれのウェイトを出して分析を行った。
対米関係よりも対米以外との関係がやや重要だとして、一対比較を行い、ウェイトを総合化すると次のような結果になった。
表3)対米関係と対米以外との関係の両方を評価基準とした分析の総合評価
|
総合得点 |
|
|
現状維持 |
0.55 |
|
引き上げ |
0.31 |
|
撤廃 |
0.14 |
※ただし、分析は富山大学のAHPシステム「Web DE AHP」を用いて行った。
(イ)評価基準のカット(分析4)
国内政治と社会問題のウェイトは0.08 、0.09 と全体に占める割合が小さいので、評価基準から除き、国際関係と経済のみで評価をした。表10は上位2項目の修正重要度である。
表4)上位2項目についての重要度
|
|
国際 |
経済 |
政治 |
社会 |
幾何平均 |
重要度 |
|
国際 |
1 |
5 |
7 |
5 |
3.64
|
0.76
|
|
経済 |
1/5 |
1 |
3 |
3 |
1.16
|
0.24
|
この修正重要度を用いたウェイトの総合化を行う。結果は表5のようになった。
表5)上位2項目の評価基準で行った総合ウェイト
|
評価基準 |
国際 |
経済 |
総合ウェイト |
|
|
ウェイト |
0.76
|
0.24 |
|
|
|
現行 |
0.64
|
0.73 |
0.660
|
|
|
引き上げ |
0.26
|
0.19 |
0.241
|
|
|
撤廃 |
0.10
|
0.08 |
0.099
|
|
5.考察
以上、4つの分析による総合ウェイトを一覧にして表6に表す。
表6)各分析の総合ウェイトの比較
|
|
分析1 |
分析2 |
分析3 |
分析4 |
|
現行維持 |
0.66
|
0.33
|
0.55 |
0.66
|
|
引き上げ |
0.24
|
0.42
|
0.31 |
0.24
|
|
枠の撤廃 |
0.10
|
0.25
|
0.14 |
0.10
|
分析1は世論調査と、分析2は政府方針と比較的よく合致しているという。つまり、世論は対米以外の多極的外交政策を重要視し、政府は対米関係を重視しているといえる。従って、今後防衛費の規模をどれくらいに決定するかは、どのような外交政策をとっていくかに大きく左右される。その場合、分析3で行ったように、対米関係と対米以外の関係を一対比較し、そのウェイトを分析に生かすこともできる。
また分析4では、重要度の低いと思われる評価基準をあらかじめ除いて分析を行った。その結果は、全ての評価基準を用いて行った分析とほぼ一致しているということから、重要度の低い評価基準を除いて分析を行うことは、手順の煩雑さを減少させ、評価の焦点を明確にできるという点から有効だといえる。
参考資料
資料1)平成12年度の防衛費
|
区分 |
平成12年度 |
|
|
防衛関係費 |
49,388億円 |
49,533億円 |
|
対GDP比 |
0.952% |
0.956% |
|
対一般歳出比 |
10.1% |
12.2% |
※ 左欄はSACO関係経費を除いたもの、右欄は含んだもの
SACO(Special Action Committee on Okinawa)
沖縄に関する特別行動委員会。沖縄に所在する米軍施設・区域に係る諸課題に関し協議することを目的として設置された日米間の委員会(95年11月設置)。
資料2)平成13年度一般歳出に占める防衛費の割合
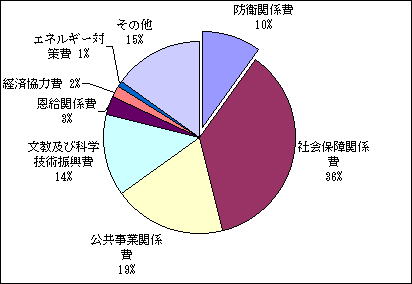 (資料1,2ともに、防衛庁ウェブサイトより引用[1])
(資料1,2ともに、防衛庁ウェブサイトより引用[1])
資料3)防衛費1%枠を巡る議論
中曽根内閣の1987年度予算案で、防衛費が国民総生産に占める割合が1・004%となり、1%を突破した。政府・自民党内には「国の根幹にかかわる防衛政策を、財政面で制約することは好ましくない」などの不満があったため、1%突破は歓迎された。
米国も政府の判断に賛辞を送ったが、中国や韓国、東南アジアなど第2次世界大戦で日本軍が攻め込んだ地域からは「軍事大国化」を心配する声が上がった。
「1%枠」は76年11月、三木内閣の時に策定した防衛計画大綱の中で位置付けられた。「各年度の防衛費は国民総生産(GNP)の1%を超えない」との方針が閣議で決まり、この「1%枠」が軍事大国化の歯止めとして内外に受け入れられてきた。
90年度にも給与の改定に伴う予算の修正で最終的に1%を突破することになったが、政府は「GNPの基準が変わる」として0・003%下回る0・997%との試算を発表して、1%枠の精神が引き継がれていることを示した。
(毎日新聞ウェブサイトより引用[2])